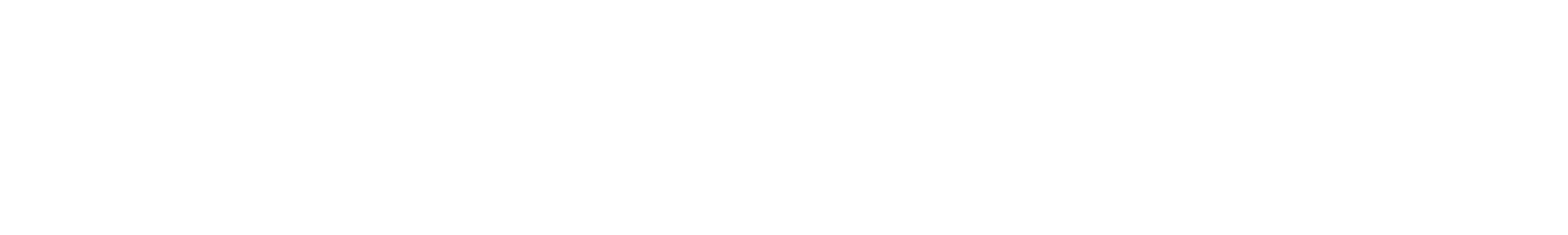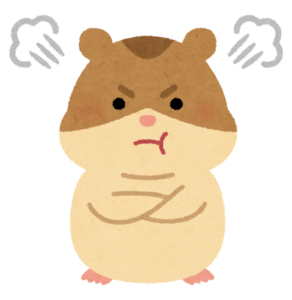別視点で支援を見直す@2025年春
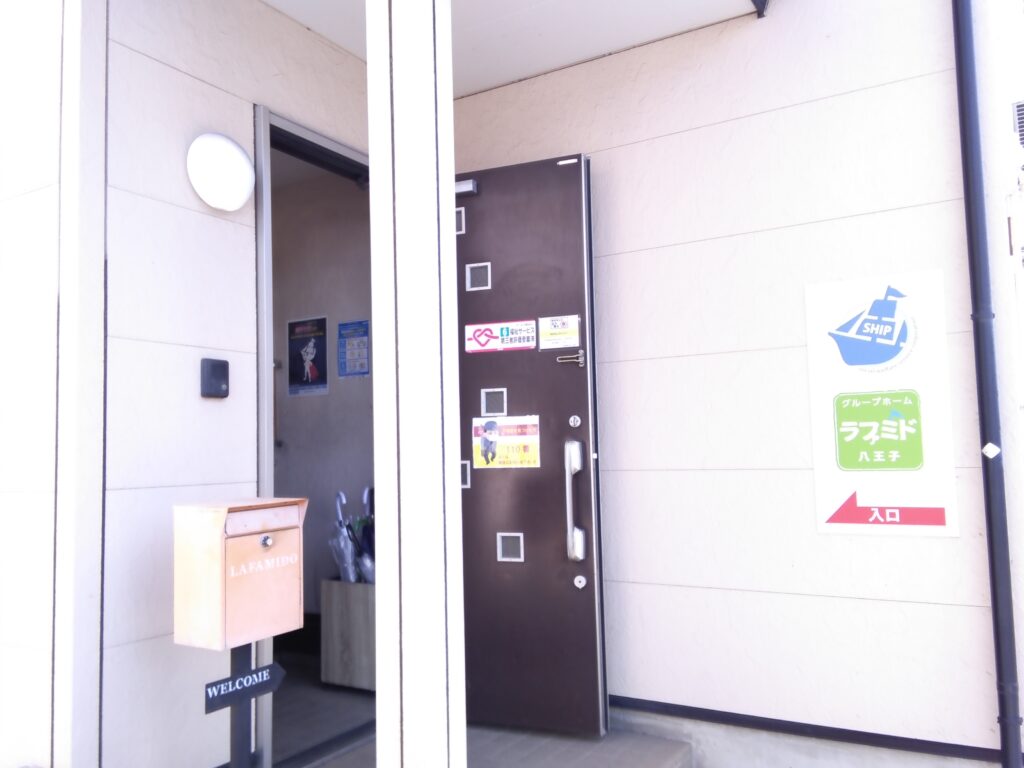
ご覧頂き、ありがとうございます。
ラファミド八王子で世話人をしている簗取と申します。
寒暖差が厳しいこの頃、
皆様は体調を崩される事なくお過ごしでしょうか。
暑いと思えば、気温が一桁台に落ちたり…
クーラーと暖房を連日に渡って
使い分ける日が来るとは思ってもみませんでした。
それに加えて、花粉や色々な粒子も飛び交っているようですね。
鼻炎薬や目薬が無いと、涙でパソコン画面が見えません。
私の場合、ビタミンや整腸剤、加齢に抗う為のサプリが欠かせない為、
服用する際の水分で少し腹が満たされてしまいます。
そしてこれは完全に私事ですが、普段の生活で色々な負荷が掛った事で、
睡眠が困難な事態になってしまい、
「なんでこんな事に」という気持ちで日々過ごすようになりました。
そもそも、今までどうやって当たり前のように眠っていたのか、
眠気はどこからやってくるのか、何時にどの姿勢で寝ていたのか、
普段考えもしなかった思考(ストレス)が芽生え始めました。
…すぐ寝たいだけなんですが、思考がまとまらない状況です。
これまでに無かった新しいストレスというのは、
一見すると見通しが立てにくいです。
「一時的な負担のはずだから、今だけ我慢すれば大丈夫」
なんていう風に切り替えて、うまく事が運べば良いんですが
「いつまで耐えればいいのか」「いつこの負担が終わるのか」
という出口の見えない不安は、他方で怒りにも変換されがちです。
それまで出来ていた事、疲労具合にすら気付けない事も多々あります。
私は、これまでアンガーマネジメントやアサーティブに関する研修を
社内で受講させて頂き、自分の怒りの性質が、
受容の器が小さく、
怒り自体が粘着質で、
それでいてすぐ沸騰するタイプという事が分かりました。
「見通しが立たずに、いつまで続くのか分からないストレス」は苦手です。
ここまで自分自身の話をしてしまいましたが、現在に至っては、
通院をしたり、身辺の環境を整える事で、ようやく落ち着きを取り戻しています。
この事をきっかけに
これまで経験してこなかったストレス、「変化を受け入れることのしんどさ」は、
障害の有無を問わず、誰にでも当てはまるのではないかと考えるようになりました。
日々の「安定」を失う事は、非常にリスキーで恐ろしい事なのかもしれません。
職務中、社内では「〇〇さんは障害特性上、変化が苦手」というワードがしばしば登場します。
これは支援上の配慮で、「環境の変化には細心の注意を払いましょう」という前提があります。
支援上では分かっていたつもりでしたが、いざ自分が変化を強制されるストレスに晒されてみると、
「変化はこんなに怖いものだったのか…」といかに己が無知だったかを思い知りました。
(※変化の代名詞、ラファミドの自販機です。商品がよく変わります。レッド〇ルがよく売れます)
今回の記事は、支援の報告ではない上、答えも出しづらい内容でした。
ただ、物の値段一つ取ってもそうですが、日々変わらないものはない状況の中で、
いかに順応する事が大変なのか、という視点が自分に加わった今日この頃です。
以前、私が書かせて頂いた記事に
【「何事もなく1日過ごせた」というだけで、生活自体が成功体験】
という内容を記述したのですが
まさか1年経って自分に返って来るとは思いもしませんでした。
安定を失う事は怖いですが、法人内の「職員への期待」という理念項目にあるように
変化を恐れずに挑戦する姿勢を、改めて意識して業務に従事しようと思います。