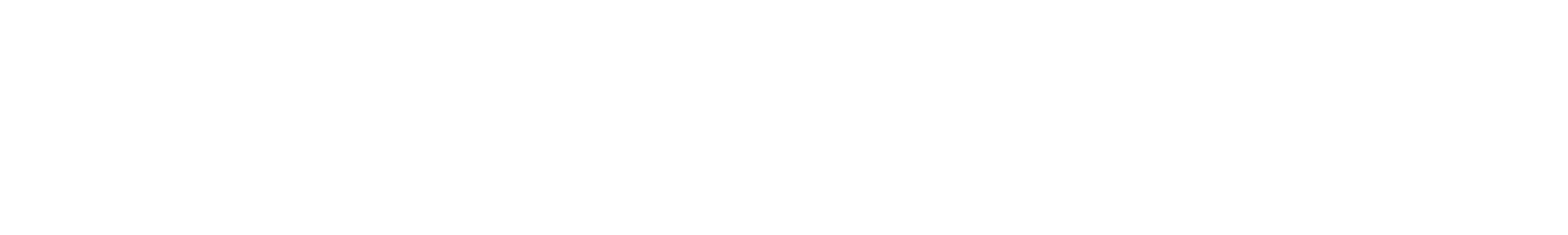カレーの作り方、だけじゃない。〜”正しさ”を教える支援から、”選べる”支援へ〜

1.カレーライスの作り方から始まった気づき
皆さま、こんにちは!
ラファミド八王子の武田です。
9月になりましたが、まだ暑さが続きますね。
最近は秋が短くなり、秋服を着る機会がほとんどなく、気づけば衣替えのタイミングを逃してしまいます。きっと同じように感じている方も多いのではないでしょうか。
さて、先日私が参加した社会福祉士養成課程のスクーリングで、こんな課題が出されました。
「カレーライスの作り方を教えてください。」
皆さまなら、どのように対応しますか?
私は迷わず「玉ねぎを切って、お肉と人参とじゃがいもを入れて…」と答えました。
しかし講師からは、こう問いかけられました。
「その人は本当にそのカレーを食べたかったのでしょうか?」
私はハッとしました。
好きな具材、辛さの好み、調理経験…何も確認せずに、自分の中の“普通”を相手に押しつけていたのです。
2.支援の基本は「個別化」と「自己決定」
この気づきは、相談援助の基本に直結しています。
利用者様から「働きたい」「一人暮らししたい」「通所できるようになりたい」とお話があったとき、支援者が「こうすればいい」と答えを教えることは支援とは言えません。
大切なのは、
-
アセスメント:背景や強み、課題、環境要因を丁寧に把握すること
-
個別化:一人ひとりの経験や価値観を尊重すること
-
自己決定の尊重:目標達成に向けて、利用者様が自ら方法を選び取れるように支えること
支援とは「やり方を教える」ことではなく、その人が目標達成に向けて自己選択できるように働きかけることであると改めて実感しました。
3.Aさまから学んだ“通所の壁”
現在担当しているAさま(40代/統合失調症)からも、同じ気づきをいただきました。
Aさまはこう話してくれることがあります。
「声に悩まされてあまり寝られなくて体調が悪いので、今日は休みます。」
日中は散歩や買い物に出られる日もあり、外出自体が難しいわけではありません。
課題は「決まった時間に、決まった形で通所すること」でした。

4.アセスメントで見えてきた課題
アセスメントを進めると、次のような課題が明らかになりました。
-
体調を整えて、決まった日に通所することの難しさ
-
作業内容に対する苦手意識
-
対人関係での緊張
-
幻聴によって十分な睡眠が取れず、不調になってしまうこと
-
自分に合った通所先を見つけられていないこと

5.課題に基づく支援の実際
こうした課題に対して、担当として次のような支援を行いました。
-
通所できた時とそうでない時の違いを整理し、要因を一緒に確認
-
通所先との情報共有を行い、無理なく取り組める工夫を一緒に考える
-
クライシスプランを作成し、体調や対処法を視覚化。朝夕の巡回時に一緒に確認
-
幻聴や疲労への対処方法を日常生活で実践と振り返り、リカバリー方法を検討
-
計画相談の方と一緒に安心して通える事業所を見学し、選択肢を広げる

6.支援の結果とその後
支援の結果、心身の不調を理由に元の通所先は退所されました。
その後、計画相談の方とともにいくつかの事業所を見学し、その中から安心して通える事業所を選び、最終的に利用契約へとつながりました。
そこは、通所日数や滞在時間の制約がなく、作業も伴わないため、自分の体調に合わせて無理なく通える場でした。
今後は定期面談や朝夕の巡回時に通所状況を振り返り、課題に対してどのように解決していけるのかを一緒に模索していきたいと思います。

7.支援の基本に立ち返って
支援者の役割は、方法を押しつけることではありません。
アセスメントや日々の関わりを通して気づきを促し、
利用者様が自分で進む方法を選択できるように働きかけること。
カレー作りと同じで、レシピを一方的に教えるのではなく、
「どんなカレーを食べたいのか」から一緒に考える。
これこそが支援の基本だと強く再確認する機会となりました。
これからも、この姿勢を念頭に置いて利用者様と関わっていきたいと思います。

8.最後に
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
当事業所では、
「支援される部分を少なくし、自分のできる部分を増やすこと」
「障碍の部分は社会資源を活用して補完し、自立へ導くこと」
という理念を大切にしています。
「自分らしい暮らしを実現したい」利用者様も、
「理念ある支援を実践したい」求職者の方も、
安心して歩みを進められるよう、私たちがサポートします。
まずはお気軽に、ご相談・見学にお越しください。